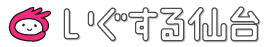世紀を超えたづんだ「村上屋餅店」

世紀を超えた「づんだ」
若草色の生地に「づんだ餅」と白抜きされたのれんをくぐると、ショーケースに餅や大福、まんじゅうが整然と並ぶ。仙台市青葉区北目町にある村上屋餅店は、今では仙台名物となった「ずんだ餅」を初めて商品化した店として知られる。
表記は「ずんだ」が一般的だが、ここでは「づんだ」。「豆を打って作る豆打(づだ)」がなまったという由来を大切にしている。
1877年の創業以来、手作りを売りにしてきた。これも店主、村上康雄さん(59)のこだわりだ。
 ▲『だれにも真似できない』と伝統の味に自信を持つ村上康雄さん=仙台市青葉区北目町の村上屋餅店
▲『だれにも真似できない』と伝統の味に自信を持つ村上康雄さん=仙台市青葉区北目町の村上屋餅店
仕込みは毎朝早くから村上さんが一人で行っている。つきたての餅を同じ重さになるように手でちぎる。づんだとなる枝豆の薄皮もひとつひとつむいて、すり潰す。絶妙な甘さの中に、しっかりと豆の味が生きている。
「こんな時こそ甘いものが食べたい」。東日本大震災の2日後、食料や物資が入ってこない状況で、再開した店の前には長蛇の列ができた。甘さに安らぎを求めた被災者の期待に応えるべく、休むことなく在庫の限り餅を練った。「材料があったから。やらない理由はなかった」
栄養価の高い餅を被災地石巻までわざわざ届けに行く客もいた。2年5カ月たった今でも、「あのときはありがとう」と店を訪れる客が後を絶たない。
手作りだからこそ生み出せる味。常連客の女性(76)は「あたしのひいおばあちゃんのころから通っているのよ」と誇らしげに話した。一緒に来ていた娘は「村上さんのづんだは特別。他の店のずんだは“づんだ”じゃないよね」とうなずきを返した。
本物の味を求めて全国から足を運ぶ人が多く、客足は10分と途切れることはない。伝統を受け継ぐ変わらぬ味は世代や距離を超え、愛される。
かつては伊達家御用達の和菓子屋だった。137年の歴史を紡いできた村上屋餅店だが、村上さんの娘二人は、それぞれ家業とは別の道を歩んでいる。だからといって、代々受け継いできた技を他人に教ええるつもりはない。「俺が死んだら、終わりだよ。だから生きてるうちに食べに来て」
笹山 大志(立命館大 2年)
ボハーチ ダービッド(東北大博士課程 2年)
遠藤 有紗(山形大 1年)
佐藤 知佳(東北学院大 3年)
※名前をクリックするとその人の個人原稿が見られます。
この記事を書いた人
- 一般社団法人ワカツクと河北新報社が主催するインターンシッププログラム「記者と駆けるインターン」。学生たちがチームを組んで、仙台の中小企業や団体を取材した記事を紹介します。ときに励まし合い、ときにぶつかりながら、チームで協力して取り組んだ“軌跡”をお楽しみに♪
この人が書いた記事
 記者インターン2019.05.09「Volume1(ver.)」人と音楽の縁結ぶ
記者インターン2019.05.09「Volume1(ver.)」人と音楽の縁結ぶ 記者インターン2019.04.25「タンヨ玩具店」お客さんと共に守る
記者インターン2019.04.25「タンヨ玩具店」お客さんと共に守る 記者インターン2019.04.11「PHOTOスタジオONE」写真で紡ぐつながり
記者インターン2019.04.11「PHOTOスタジオONE」写真で紡ぐつながり 記者インターン2019.03.28「Lamp of Hope」希望の灯火きっかけに
記者インターン2019.03.28「Lamp of Hope」希望の灯火きっかけに