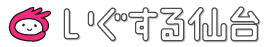物でつながる、世代を超えた思い「奥江呉服店」

着物でつながる、世代を超えた思い
母との思い出が詰まった着物の無残な姿に、言葉を失った。東日本大震災からひと月余りたった2011年4月中旬。仙台市若林区荒浜の南部くに子さん(72)は、津波で3キロ流された自宅から、泥とカビにまみれた薄紫の着物が見つかったことを、娘からの電話で知った。
震災前に、孫娘に成人式の振袖をあしらってくれた呉服店の名が浮かんだ。若林区荒町の奥江呉服店。27点の着物や小物が、「着物が好きだから、元に戻したい」という南部さんの思いと一緒に託された。
奥江呉服店は1921年創業。若女将の佐藤東代さん(45)によると、荒浜地区には同店の常連客が多い。震災直後には、津波をかぶった着物や小物ざっと400点が同店に持ち込まれた。
洗いや加工は、それぞれの専門業者に依頼する。繊維が縮んだり、溶けたりした着物は直せないが、わずかでも修復の可能性があれば、全国各地に電話をかけ続けた。
「復元を頼んだ取引先も、うちと何度も連絡を取り合いながら苦労してくれました」。佐藤さんは振り返る。
 ▲奥江呉服店若女将の佐藤東代さん=仙台市若林区荒町
▲奥江呉服店若女将の佐藤東代さん=仙台市若林区荒町
辛かったのは、修復不能な着物の処分。「着物は何世代も受け継がれるものだし、宝物なんです。それなのに捨てなければいけないのは、心苦しかったですね」
薄紫の着物は、幼かった南部さんが蚕から絹糸を紡ぎ、母親が糸を染めて作った母子の共同作品。南部さんは現在、若林区の七郷中央公園仮設住宅で暮らす。居室が2部屋しかなく、収納も狭い。まだ薄紫の着物は手元に戻っていないが、修復の工程を聞いた南部さんは「あんなに一生懸命直してもらってねえ、奥江呉服店さんには本当に感謝しています」と話す。
「着物には、世代を超えて家族のつながりを感じさせてくれる力がある。呉服店は、できることをしているだけ」と佐藤さん。「だって、私達は90年間お世話になっているんです」と、老舗の誇りを少しだけのぞかせた。
金野 正史(国際自然環境アウトドア専門学校 2年)
水上 奨之(東北学院大 2年)
金森 なつ実(東北大 3年)
小林 智都(慶應義塾大 3年)
※名前をクリックするとその人の個人原稿が見られます。
この記事を書いた人
- 一般社団法人ワカツクと河北新報社が主催するインターンシッププログラム「記者と駆けるインターン」。学生たちがチームを組んで、仙台の中小企業や団体を取材した記事を紹介します。ときに励まし合い、ときにぶつかりながら、チームで協力して取り組んだ“軌跡”をお楽しみに♪
この人が書いた記事
 記者インターン2019.05.09「Volume1(ver.)」人と音楽の縁結ぶ
記者インターン2019.05.09「Volume1(ver.)」人と音楽の縁結ぶ 記者インターン2019.04.25「タンヨ玩具店」お客さんと共に守る
記者インターン2019.04.25「タンヨ玩具店」お客さんと共に守る 記者インターン2019.04.11「PHOTOスタジオONE」写真で紡ぐつながり
記者インターン2019.04.11「PHOTOスタジオONE」写真で紡ぐつながり 記者インターン2019.03.28「Lamp of Hope」希望の灯火きっかけに
記者インターン2019.03.28「Lamp of Hope」希望の灯火きっかけに