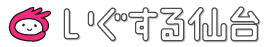着物でつなぐ、人と家族

赤、緑、黄色。日常では見られない色のカビが、400点以上の着物を覆っていた。かつて、祝いの象徴だったそれら着物は、カビと、津波から異臭でその面影を無くしていた。
東日本大震災から約1か月経った頃、仙台市若林区にある奥江呉服店に、400点以上の、津波による泥が付着した着物が並んでいた。その多くは同じ若林区の沿岸部、荒浜地区で被災した人々が持ってきた着物だ。「自分で処分するのはつらい。処分するかしないかは、奥江さんに任せる」。そう言って店を訪れた客のほとんどは、世代を超えての付き合いがある常連さん。奥江呉服店は「あとでいいから」と、お金もとらなかった。
震災によるの経営不安よりも、大切なものがあった。
「確かに、目先だけをみたら厳しいかもしれない。けど、今までもお世話になってきたし、長い目で見れば、当たり前のことなんです」。奥江呉服店の若女将、佐藤東代(44)さんは言う。
顧客と売り手という関係を超えた、信頼と地域への愛着からの行動だった。

▲奥江呉服店若女将佐藤東代(44)さん=仙台市若林区荒町
客は、着物を買うためだけに奥江呉服店を訪れない。ただ、世間話をして、お茶を飲みにやってきたお客さんもいる。震災当時は、呉服店に16人ほどの人が避難をした。そこで暖をとりながら、近所の人の安否確認、新しい住居の場所など、互いに互いを気遣い、情報交換も行った。
荒浜地区で被災をした南部くに子さん(72)もその常連さんの一人。津波で汚れた27点の着物を奥江呉服店へ持って行った。彼女の家の一階部分は津波で壊滅してしまったが、幸いにも2階部分は自宅から3・離れた田んぼの上で発見された。着物をしまっていた場所が2階であったため、浸水はしたものの、助かった着物が多数あった。
「着物は一生だからねぇ。3世代、4世代にもわたるんだよ」。南部さんは、着物への想いをそう語る。津波で汚れてしまった着物の中には、再来年に成人式を迎えるお孫さんへの着物や、南部さんの母が織った、手織りの着物もあった。孫の成人式、母の手織。南部さんにとって着物は、家族の歴史をつないでいくものだった。
着物。それは、めでたい日には家族を繋ぎ、震災時には人をつないだ。時代が移り変わる中でも変わることのないつながりは、着物によって受け継がれる。これからも奥江呉服店は若林区の人々のために、その着物を通して、家族の歴史をつなぎ、人をつなぐ。
この記事を書いた人
- 慶應義塾大学総合政策学部総合政策学科3年
この人が書いた記事
 記者(個人)2014.03.02継続した震災遺児支援を
記者(個人)2014.03.02継続した震災遺児支援を 記者(個人)2014.02.27着物でつなぐ、人と家族
記者(個人)2014.02.27着物でつなぐ、人と家族 お仕事2013.10.31大切なのは継続。震災遺児支援に取り組み続ける「家庭教師、個別指導のアップル」
お仕事2013.10.31大切なのは継続。震災遺児支援に取り組み続ける「家庭教師、個別指導のアップル」