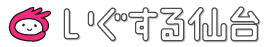つなげ、着物に込めた思い

青、金、緑、オレンジ、鮮やかな赤。着物の上に、5色以上の斑点が散らばっている。これは着物の模様ではない。カビである。津波に襲われた着物は、元のきれいな薄紫色を失ってしまった。
薄紫色の着物の持ち主は、現在仙台市若林区の七郷中央公園にある仮設住宅で暮らす南部くに子さん(72)。若林区荒浜にあった南部さんの家の1階部分は壊滅してしまったが、着物をしまっていた2階部分は、自宅から3km離れた田んぼの中で発見された。薄紫色の着物は、南部さんが幼いころに蚕から絹糸を紡ぎ、母親が糸を染めて作ってくれた思い出の着物だった。
「着物が好きだから元に戻したくてねえ。一度孫が成人式の振袖を借りた奥江呉服店に頼もうと思ったのよ」と南部さんは話す。
若林区荒町にある奥江呉服店は1921年創業。震災後、津波を被った着物や小物が400点持ち込まれた。洗いや加工は、それぞれの専門業者に依頼する。繊維が縮んだり、溶けたりした着物は直せないが、わずかでも修復の可能性があれば、全国各地に電話をかけ続けた。
「復元を頼んだ取引先も、こちらと何度も連絡を取り合いながら苦労してくれました」と奥江呉服店若女将の佐藤東代さん(45)は振り返る。「着物は何世代も受け継がれるものだし、宝物なんです。それなのに捨てなければいけなかったのは心苦しかったですね」
着物にはその家々の思いが込められる。
 ▲着物に込められた思いについて語る佐藤さん
▲着物に込められた思いについて語る佐藤さん
「成人式、七五三と大切な節目に孫に着物を着てもらうことで、おじいちゃん、おばあちゃんは、成長を実感できるんです。けれど、このような思いがあるなんて孫は後になってみないとわからないものですよね」。東代さんは微笑みながら言う。
着物を与えられる側が着物を与える側になって初めて知る、着物を着せる意味。時代が移り変わる中でも、変わることのない家族の思いとつながりは着物によって伝えられていく。