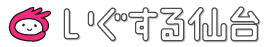本当の“復興”

「着物を着たらねぇ、ルンルンになっちゃうんだよ」
そう笑顔で語りながら着物を広げて見せるのは、東日本大震災で自宅が被災し、仙台市若林区の七郷中央公園仮設住宅で一人暮らしをしている南部くに子さん(72)。

▲「着物が好きなの」と語る南部さん=七郷中央公園仮設住宅
南部さんは着物や小物合わせて数十点を所有していたが、津波により元の場所から3キロ離れた場所で泥や砂にまみれ、油がこびりつき、カビが生えたりしていた状態で見つかった。
それを娘からの電話で聞いた南部さんは呆然とした。着物の中には、南部さん自身が蚕から糸をとり、母親がその糸を染めて紡いだ薄紫の着物なども含まれていたからだ。
「着物が好きだから、元に戻したかったんだよ」
南部さんの頭の中に孫娘の振り袖をあしらった呉服店の名が浮かんだ。若林区荒町の奥江呉服店だった。奥江呉服店は1921年創業。若女将の佐藤東代さん(45)によると、荒浜地区には常連客が多い。震災後には、津波に巻き込まれた着物や小物が持ち込まれ、その数は数百を超えていた。
洗いや加工はそれぞれの専門業者に依頼する。しかし、繊維が縮んだりして、修復が不可能な物は依頼者に断り断腸の思いで捨てる。助かる見込みのあるものは修復するまで死力を尽くした。泥や砂、油、カビなど複合的な汚れを丁寧に取り除いていくために、汚れの具合を1点1点専門業者と相談し合いながら修復を進めていった。
奥江呉服店では修復が終わった着物を車に積み込み、着物を預けた人の元へと走り回った。「本当にありがたくてねぇ。感謝しかなかったわ」。着物を直接受け取った南部さんは語る。
戻ってきた着物や小物の中には、汚れが消えて戻ってきたものや、どうしても汚れがシミになって残ってしまったものもあるが、南部さんはどれも同じようにいたわっている。
しかし、戻ってきた着物に袖を通すことに南部さんはためらいを感じている。
「被災者なのになんで着物を着てるんだ、って言われるんじゃないかと思ってね。なんとなく気兼ねしちゃうの」。南部さんは困ったように微笑む。
南部さんが何のわずらいもなく、ルンルンな気持ちで着物に袖を通せるときは何時訪れるのだろうか。