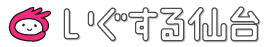地元野菜が命つないだ「今庄青果」

2018年2月から3月にかけて、河北新報社と一般社団法人ワカツクが主催した、記者インターンシッププログラム「記者と駆けるインターン」。参加学生が執筆した記事を紹介します!
地元野菜が命つないだ
「まいど!今日は仙台雪菜がお勧めだよ~」。語尾に力のある威勢の良いかけ声に、買い物客の顔がほころんだ。
仙台市青葉区中央、JR仙台駅前の仙台朝市で創業61年を迎えた「今庄青果」。宮城県産を中心に300種類近い野菜や果物がひしめき合う店内は、新鮮さゆえに、独特の青臭さも漂っていた。

創業者の父と店を仕切る専務の庄子泰浩さん(57)は、地元産、特に曲がりネギや仙台白菜などの伝統野菜を大切にする。店頭で勧めるばかりでなく、市民向けに伝統野菜の講演会を開いたり、子どもたちと地元野菜を使った料理を考案するイベントを仕掛けたりと、地元産の良さを知ってもらう活動に熱心に取り組む。
「その原点は中学時代」と庄子さんは明かす。通学途中、近所の農家の女性にもらったトマトで世界が変わった。採れたてではあったが、それ以上においしく感じた。「傷つきやすい野菜だからね、市場に出せないの。だから、おいしい」。女性の言葉が心に引っ掛かった。
スーパーに並ぶ野菜はどれも形が良く、傷もなくきれいだ。品種改良され、日持ちもする。だが、あのトマトのようなうまさはない。庄子さんは「不格好でも、おいしい野菜を届けたい」と思うようになり、やがて後を継ぐことを決意した。

今庄青果は地元農家からの直接仕入れを重視する。市場には出回らない“実はおいしい野菜”を店頭に並べるためだが、その姿勢が強みを発揮したのが東日本大震災。生鮮食品の流通がまひし、シャッターを下ろすスーパーや飲食店が相次ぐ中、地元農家のネットワークを駆使して野菜をかき集め、路地売りながら震災翌日から1か月間、1日も休まず店を開け続けた。「地産地消が根付いていたからこそ乗り切れた」。
震災発生から7年がたち、庄子さんは「食を通じて地域に結び付きをつくりたい」との思いを強くする。住民同士がつながる場を提供しようと、みそ造りのイベントを開くなどしている。「八百屋の“八百”には“数え切れないもの”という意味がある。野菜を売ること以外でも地域に貢献したい」と力を込めた。
取材後記
就職活動を間近に控え「自分に何ができるか」と考えたときに、まず自分の故郷・東北と向き合ってみようと参加した今回のインターン。取材先選定にあたって仙台朝市を歩いていると、店員と客の会話で賑わう「今庄青果」で足が止まりました。話を聞くうちに、東日本大震災では、60年もの間、仙台朝市で市民の胃袋を支えてきた“今庄青果だからこそ見えたもの”があるのではないかと考え、取材をお願いしました。
取材を重ねる中で、私たちの知らない震災後の仙台が次々と姿を現しました。客が自ら野菜の包装を手伝い、笑顔で溢れた仙台朝市。流通が破綻していた際に活きた地元農家との関係。避難所に引きこもりただただ悲嘆に暮れるのではなく、共助の輪を広げようと誰もが手をつなぎ、励まし合った明るい一面を初めて垣間見ました。同時に、援助を待つよりまず自分たちで行動しようという姿勢こそが、復興を前に進めるのだと思いました。
震災から7年経った今、東北に伝えるべきことは何か。学生である私たちだからこそ訴えられることはあるか。取材メモと向き合いながら本当に悩みました。しかし最終的に読者の心に響くのは、自分が素直に喜怒哀楽したことだと気が付きました。記者に必要なのは、抜かりない知識やずば抜けた作文能力ではなく、森羅万象と真正面から向き合い、感動したり、時には憤ったりする豊かな感受性だと思います。これからも周りにアンテナを張り続けたいです。
取材協力
今庄青果 http://www.imasho-seika.jp/
文・写真
河北新報社インターンシップ17期B班
埼玉大学3年 木村みなみ(2018年3月当時)
この記事を書いた人
- 一般社団法人ワカツクと河北新報社が主催するインターンシッププログラム「記者と駆けるインターン」。学生たちがチームを組んで、仙台の中小企業や団体を取材した記事を紹介します。ときに励まし合い、ときにぶつかりながら、チームで協力して取り組んだ“軌跡”をお楽しみに♪
この人が書いた記事
 記者インターン2019.05.09「Volume1(ver.)」人と音楽の縁結ぶ
記者インターン2019.05.09「Volume1(ver.)」人と音楽の縁結ぶ 記者インターン2019.04.25「タンヨ玩具店」お客さんと共に守る
記者インターン2019.04.25「タンヨ玩具店」お客さんと共に守る 記者インターン2019.04.11「PHOTOスタジオONE」写真で紡ぐつながり
記者インターン2019.04.11「PHOTOスタジオONE」写真で紡ぐつながり 記者インターン2019.03.28「Lamp of Hope」希望の灯火きっかけに
記者インターン2019.03.28「Lamp of Hope」希望の灯火きっかけに